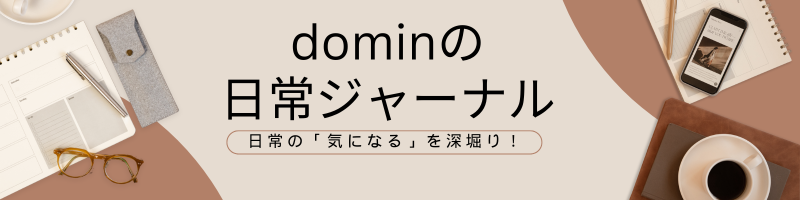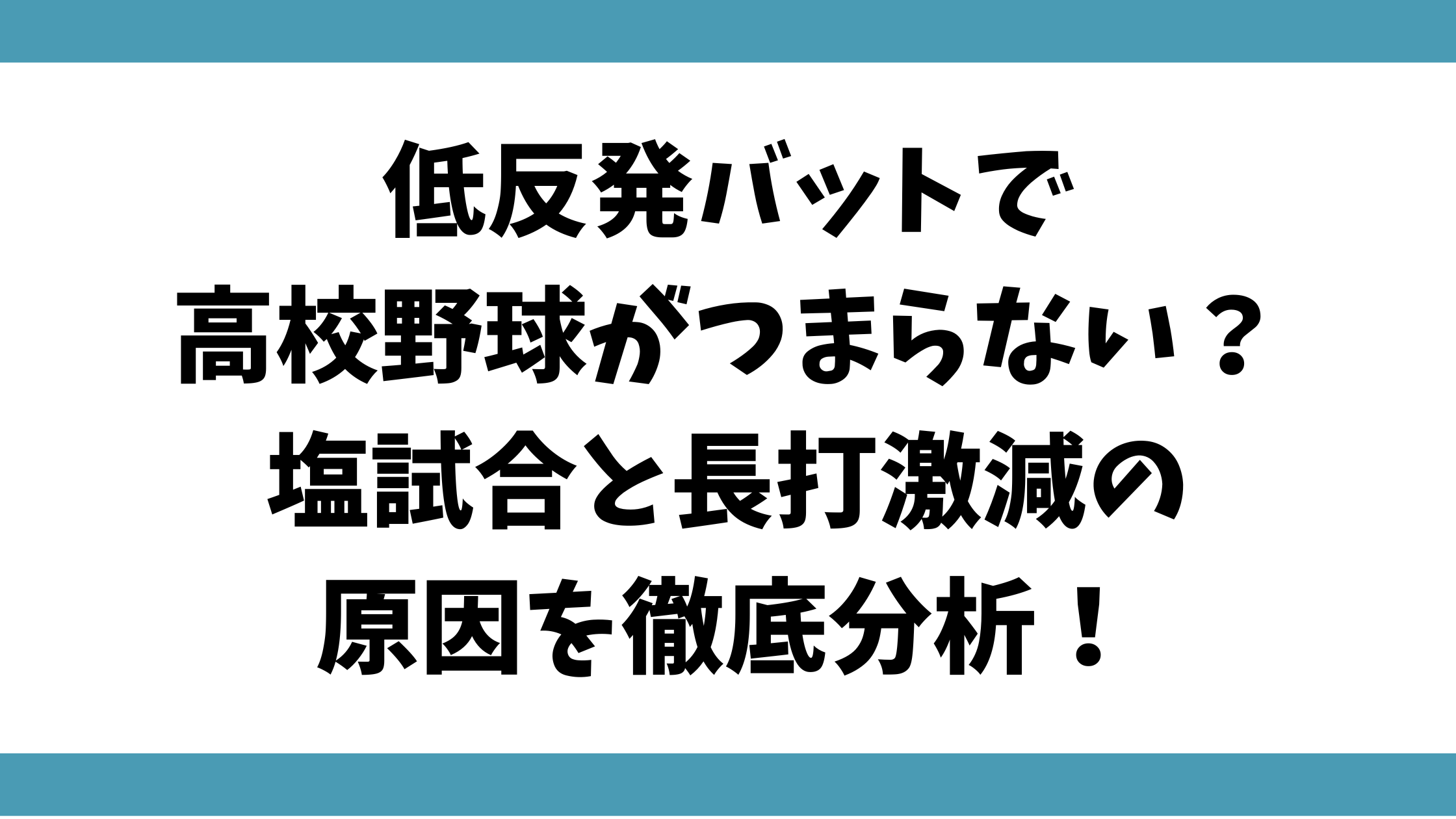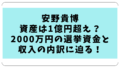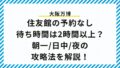高校野球で低反発バットが導入されて試合がつまらなくなったのか、長打や本塁打が減ったのは本当なのか、徹底分析します。

高校野球を観ていて「なんだか地味になった」「試合が盛り上がらない」と感じたことはありませんか?
その原因として注目されているのが、2024年から全面導入された「低反発バット」です。
ホームランや長打が減り、点の取り合いではなく、いわゆる塩試合が増えたとも言われています。
しかし本当にそれだけが理由なのでしょうか?
本記事では、低反発バットで高校野球が本当につまらなくなったのか?試合データをもとに「つまらなくなった」と言われる背景を多角的に分析します。
低反発バットで高校野球が「つまらない」は本当?SNSの声から検証
「高校野球がつまらなくなった」と感じている人が、SNSやネット上で増えています。
とくに話題になっているのが、新しく導入された低反発バットの影響です。
「点が入らない」「長打が出ない」「試合が盛り上がらない」といった声が多く、なかには「これでは高校野球が変わってしまう」と嘆く人もいます。
ここでは、実際のSNSの声と、ファンが感じている「つまらなさ」の理由を見ていきます。
X(旧Twitter)に投稿される「塩試合」「飛ばない」の声
新しい低反発バットが使われるようになってから、「高校野球がつまらなくなった」という声がX(旧Twitter)に多く見られます。
高校野球の低反発バット良くないね🫠
— ゴリヶ丘学園初代学長 (@gorigaoka) July 29, 2025
今年の地方予選は接戦が多いんじゃなく、塩試合が多いだけ🙌点が入らないからタイブレークまでもつれてるだけ🍌🍌
中学生のスカウトは打てる打者捨てて守備と走力重視で取って行けば全国近づくかもね🙌打者は打つ必要無し、立って四球狙い徹底すればほぼ勝てる💔
とくに目立つのは、「点が入らない」「塩試合ばかり」という不満です。
- 「延長戦が多いけど、点が取れないだけで接戦ではない」
- 「強打者より、走れる選手や守れる選手のほうが重視されてきた」
- 「春のセンバツはつまらなかったが、夏には各校が対応してきて改善された」
- 「ポテンシャルよりチームワークが勝敗を分ける時代に変わった気がする」
なかには「新基準バットにも慣れてきて、夏は面白くなってきた」という前向きな意見もありますが、全体的には「飛ばないバット=試合が地味になった」という印象が広がっているようです。
春のセンバツ高校野球は新基準の低反発バットの影響で打球が外野に飛ばなくて塩試合連発でつまらなかったけど、夏の大会に入ってからは各チームが低反発バットに対応してきて強烈な打撃が見られるようになって面白くなってきた😎
— yuu (@yuu_experiments) July 26, 2024
新基準の低反発バット否定派
同時にプロ野球の飛ばないボールも大反対
ファンが「つまらない」と感じる3つの理由
高校野球が「つまらなくなった」と感じる人には、いくつか共通した理由があります。
Xや知恵袋でのファンの投稿から、特に多く見られた意見を3つにまとめました。
- 観ていて盛り上がる「大きな当たり」が少なくなり、試合が地味に感じる
- 「打撃のドラマがなくなった」「記録が出ない」という声も
- バットの影響で打球の勢いや軌道が変わり、守備がミスしやすくなった
- 「守備の基本ができていない」という厳しい意見も
- 打球の勢いが死ぬことで、これまでなら抜けていた打球が内野手の前に残り、処理が難しいハーフバウンドになりやすくなったことも一因と考えられます
- 得点が少なく、長い試合が増えた
- 延長タイブレークに入っても盛り上がらない、という声も
もちろん「点を取る工夫を見るのが面白い」と前向きな意見もありますが、多くのファンが以前の高校野球らしさを懐かしんでいるようです。
低反発バットで本当に長打は減った?データで見る変化
低反発バットが導入されたことで、本当に打球は飛ばなくなったのか。
その疑問に答えるためには、実際のデータと選手たちの声を見ていく必要があります。
本塁打数や飛距離がどれだけ減ったのか、そしてどのような打撃技術が求められるようになったのか。
ここでは、数字と現場の体感の両面から、バット変更の影響を詳しく見ていきます。
導入後の本塁打数や飛距離
低反発バットの導入によって、打球の勢いや飛距離が目に見えて落ちたと言われています。
日本高等学校野球連盟のYouTube動画「新基準金属製バットについて」によると、新基準の低反発バットは、従来のバットよりも打球初速が3.6%減少していることが明らかにされています。
打球初速が3.6%減少したことにより、打球のスピード(初速)は平均で約5キロ減少。飛距離も5〜6メートルほど短くなっているとのことです。
この原因は、バットの反発力を意図的に下げたこと。
バットがボールを弾く力が小さくなり、いわゆる「トランポリン効果」が弱まったことが大きな理由なのです。
特に大きな変化が見られたのは、甲子園での本塁打数。
低反発バットが本格導入された2024年の春のセンバツ大会の記録を見てみると、これまでに比べてホームランの本数が極端に少なくなっています。
| 年・大会 | 本塁打数 |
|---|---|
| 2022年 春 | 18本 |
| 2023年 春 | 12本 |
| 2024年 春 | 3本(うち1本はランニングHR) |
地方大会でも本塁打が減っており、岐阜新聞デジタルによると2024年の高校野球岐阜大会では過去20年と比べて本塁打4割減という報道もあります。【参考情報】岐阜新聞デジタル
数字を見ても、バットの変化が試合に大きく影響していることは明らかです。
求められる打撃技術の変化とは?
低反発バットの導入で、打球が飛ばなくなっただけでなく、「芯でとらえないと全く飛ばない」という変化が起きています。
プロのように、ミリ単位で芯をとらえる力が求められるようになったのです。
仙台育英の須江監督は、「飛ばなくなったのではなく、芯が狭くなった」と話しています。

以前のバットなら、多少ズレていても外野まで運べた打球が、今では内野ゴロやポテンヒットになるケースが増えたと言っていいでしょう。
選手たちも、「前のバットならホームランになっていた」という感覚を口にしています。
とくに詰まった打球は、勢いがなくゴロになりやすくなっていると言えますね。
- より正確なミート力
→ 少しでも芯を外すと打球が飛ばないため、当てる技術が何より重要に。 - コンパクトなスイングと状況判断
→ 無理に長打を狙うより、確実にランナーを進める打撃が重視されるように。
つまり、ホームランを狙う豪快な打撃よりも、「確実に1本を狙う打者」が評価される時代に変わりつつあるのです。
プレーはどう変わった?戦術から見る新しい高校野球
低反発バットの導入によって、これまでの「打って勝つ野球」から「守って勝つ野球」へと戦い方が大きく変わってきました。
ホームランが激減した今、1点をどう取るかがより重要になり、バントや盗塁、走塁といった細かなプレーが勝敗を左右する場面が増えています。
ここでは、戦術の変化とともに注目を集めるプレーについて見ていきます。
「打って勝つ」から「守り勝つ」野球へのシフト
低反発バットの影響でホームランが減り、今までのように「打って大量点を取る野球」が難しくなりました。
そのため、多くのチームは1点を確実に取るための「スモールボール」戦術に切り替えています。
たとえば、次のような作戦が重視されるようになっています。
実際に、2024年春のセンバツ大会ではホームランがたった3本に減った一方で、盗塁や特に送りバントの数は前年を上回ったという報道がなされています。
【参考情報】【高校野球】2024年春に導入された新基準の低反発バットとは?目的や影響について解説
| 指標 | 2023年 | 2024年(新バット) |
|---|---|---|
| 本塁打数 | 12本 | 3本(75%減) |
| 盗塁・犠打 | データなし | 増加傾向あり |
※公式の比較データは発表されていませんが、各メディアで増加傾向と報じられています。
また、打撃指導にも変化が出てきました。
以前のようにフライを狙うよりも、ライナーやゴロでヒットを狙うスタイルが重視されるようになっています。
外野の頭を越すホームランではなく、外野の間に落とすヒットや俊足を生かした三塁打など、打撃のスタイル自体が変わってきたのです。
注目度が上がるバント・盗塁・走塁技術
長打が減ったことで、「小さなプレー」の大切さが目立つようになりました。
とくに、バントや盗塁、そして走塁の技術が試合を左右する場面が増えています。
たとえば、1点差で迎えた終盤、次のようなプレーが試合を決めることがあります。
- バントでランナーを得点圏に送る
- スタートの良い盗塁で相手バッテリーにプレッシャーをかける
- ランナーがゴロで一気に三塁を狙うなど、判断力のある走塁
これまでは見逃されがちだったこれらの動きが、今ではスカウトや解説者の間でも評価されるようになってきました。
さらに、守備のプレッシャーも増しています。

盗塁を防ぐ送球の正確さや、ゴロをさばいてアウトにするスピードなど、守備力がより勝敗に大きく影響する時代に入ったと言えますね。
今の高校野球では、「豪快な一発」よりも「緻密な一手」が求められるようになっています。
その結果、細かいプレーに強いチームが上位に進出する傾向が強まっているのです。
【そもそも】なぜ低反発バットは導入された?
低反発バットの導入は、単なる道具の変更ではなく、高校野球のあり方そのものを見直す大きなきっかけとなりました。
とくに注目されたのは、選手の安全性の確保と、これまで有利すぎた打者と投手のバランスを整えることです。
ここでは、この新しいバットがなぜ導入されたのか、その背景にある理由と目的をわかりやすく見ていきます。
一番の目的は「投手の障害予防」
低反発バットが導入された一番の理由は、選手、特に投手の安全を守ることです。
これまで、高反発のバットで打たれた強い打球が投手を直撃し、顔面を骨折したり、命に関わる事故が起きたりしてきました。
こうした悲しい出来事が、高野連に対策を求める声を強めたのです。

強い打球が増えることで試合が長引いて、投手の球数も増えてしまっていることも問題視されていましたよね。
全力投球が続くと、肩やひじへの負担が大きくなり、将来まで影響するケガの原因にもなります。
今回の新バットは、単なる「飛ばないバット」ではなく、選手の命と体を守るための工夫がつまった道具なのです。
打球を少しでもやわらかくすることで投手を守る、この大きな目的が、変更の背景にはあります。
「打高投低」から「本来の野球」へ
もうひとつの目的は、今まで続いてきた「打つ側が有利すぎる野球」を見直すことでした。
高反発バットの時代は、少し芯を外しても外野まで打球が飛び、投手は不利な条件で戦わざるをえませんでした。

このままでは、「投手が疲れやすい」「守りにくい」「一発で流れが変わる」という状態が続き、高校野球らしい粘り強い戦いができなくなってしまいます。
そこで「もっとバランスの取れた野球にしよう」という考えのもとで、ルール改定が行われたのです。
飛ばないバットになった今、1点を守るための守備、粘り強い投球、小さなプレーを積み上げる攻撃、まさに「原点に帰る」ような野球が求められています。
華やかさは少し減っても、本来の面白さを大切にしたいという思いが、新ルールには込められているのです。
まとめ:高校野球はつまらなくなったのか?新しい時代の楽しみ方
低反発バットの導入で、ホームランが少なくなり、「つまらない」と感じる人が増えています。
ですが、その分だけ野球の楽しみ方が少し変わってきています。
これからの高校野球では、こんな場面に注目してみてください。
たしかに派手な打撃戦は減りましたが、小さなプレーが試合を動かす、手に汗にぎる展開が増えているとも言えます。
「飛ばないからつまらない」ではなく、「どうやって勝つかを考える野球」になっているのです。
これからは、そんな新しい高校野球の魅力にも目を向けてみてはいかがでしょうか。
次の試合では、ぜひバントや進塁打に注目してみてください。
1点を取るための監督の意図が見えてきて、これまでとは違う面白さを発見できるはずです。
強打者のフルスイングだけでなく、一塁走者のリードの大きさにも注目してみましょう!